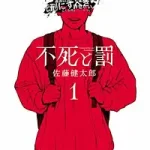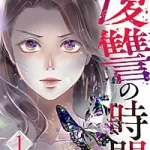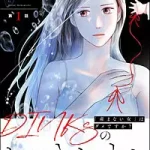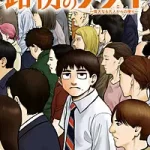絶望の淵で、少女は“もう一人の自分”と出会った――。
「パラサイト・ドール」は、壮絶ないじめ描写と、その裏側に潜む人間心理の奥深さで話題を呼んでいる作品です。
被害者と加害者、表と裏、善と悪。
その境界が溶けていくような、ぞわ…っとする感覚が、一度ページをめくったら止まらない中毒性を生んでいます。
そして何より、この作品がすごいのは、“復讐”という行為の痛快さと、それに対する居心地の悪さの両方を描いていること。
ただスカッとするだけでは終わらない、読後に残るモヤモヤこそが、この物語の最大の魅力かもしれません。
今回は、そんな「パラサイト・ドール」のあらすじや登場人物、感想レビューまでを網羅的にお届けします。
この記事を読み終える頃には、きっとあなたも…この物語の深淵を覗きたくなっているはずです。
パラサイト・ドールあらすじと登場人物

↑当サイト作成イメージ画像
- 本日
- 週間
- 月間
あらすじを簡単に紹介
ある朝、私がこの漫画を初めて読んだのは通勤電車の中でした。
「やめておけばよかった…」そう思ったのは、強烈な“読後感”が頭から離れなかったからです。
主人公・多恵は名家の令嬢。
誰もがうらやむ容姿と頭脳を持ちながらも、学校ではリリナを筆頭とした女子グループから執拗ないじめを受けています。
その内容は悪質で、性をもてあそぶような陰湿な手口。
読んでいて息が詰まりそうな描写も少なくありません。
ふと、多恵は絶望の中で命を絶とうとします。
しかしその瞬間、彼女の前に現れたのは“めぐみ”という、どこか狂気を孕んだもう一人の自分。
冷やり…と背筋を撫でる感覚。
めぐみは一方的に「入れ替わろう」と告げ、多恵の生活を引き継ぎます。
そこからの展開が怒涛です。
教師も、いじめグループも、次々とめぐみの手によって暴かれ、制裁されていきます。
でも、どこか…やりすぎなんです。
めぐみの正義は、ただの復讐に見えてきて、読者の心を不穏に揺らします。
正直、「あれ? これってスカッと物語じゃなかったの?」と戸惑うこともありました。
私自身、めぐみに肩入れしながらも、「これで本当にいいのか…?」という不安が拭えませんでした。
物語が進むにつれ、登場人物たちの立場や見方が何度も揺れ動きます。
いじめっ子だったリリナが孤立し、逆に多恵(めぐみ)にすり寄ってくる場面では、読者の感情も揺さぶられることでしょう。
この漫画は単なる“いじめ復讐劇”ではありません。
アイデンティティ、自己肯定感、罪と赦し――深く考えさせられるテーマが随所にちりばめられています。
そして、読めば読むほど「自分だったら…」と考えさせられるんです。
もし、あなたが明日、別人として生き直せるとしたら――どうしますか?
そんな問いを、作品はずっと投げかけ続けてきます。
この物語は、ただのフィクションではありません。
誰の心にも潜む「もう一人の自分」と向き合う旅なのかもしれません。
ネタバレなしで楽しむポイント
「重そう…」と身構えてしまう読者もいるかもしれません。
ですが、安心してください。
確かにテーマは重厚ですが、読み進める手が止まらない“吸引力”が、この作品にはあります。
ページをめくるたびに「次、どうなるんだ…」と、胸がざわ…っと波立つ展開の連続。
それでも、ただ暗いだけではありません。
めぐみの行動にはどこか快感すら覚える大胆さがあり、読者にカタルシスを与えてくれます。
さらに注目したいのが、作画の繊細さ。
特に登場人物の表情の描き分けは見事で、リリナの強がりの裏にある脆さや、めぐみの狂気に宿る儚さなど、視覚的な情報だけで心理が透けて見えるようです。
私は1巻を読んだ直後、「ちょっとだけ…」のつもりで2巻に手を伸ばし、気づけば20巻まで一気読みしていました。
それほどまでに、この作品の物語構造と感情設計は精密にできています。
それでも、すべてが明かされるわけではありません。
謎が謎を呼ぶ展開も多く、「もしかしてこのキャラの本心って…?」と、読み手の想像力を刺激してきます。
つまり、物語に“参加させられている”感覚があるんです。
ただの読み手ではなく、自分自身がこの歪んだ世界に巻き込まれていくような。
そう感じるのは、私だけではないはずです。
もしあなたが、ただスカッとするだけの物語に飽きているなら――この作品は、刺さるかもしれません。
闇の中に光を見つけるような感覚。
「読んでよかった」と、心の奥がそっと震える読書体験が、ここにはあります。
主な登場人物とその関係
多恵
多恵は名家の娘で、学園内では表向きは恵まれた存在に見えます。
しかし裏側では、リリナを中心としたグループから執拗にいじめられる日々を過ごしています。
その姿に「本当にこれでいいのだろうか…」と読者は胸を痛めるかもしれません。
私自身も初めて読んだとき、彼女の孤独な心情に強い共感を覚えました。
授業中にふと机に視線を落とす描写や、教室の隅で押し殺すように息をつく場面では、胸の奥にずしりと重さを感じました。
多恵の存在は、弱さと強さが交錯する人間の複雑さを体現しているでしょう。
そして彼女が自分の殻を破り、自分自身で未来を切り開いていくとき、読者は一点の光が見えたような希望を覚えるのではないでしょうか。
未来を考えるなら、彼女が自分の意思で立ち上がる瞬間こそが、最大の見どころになるのかもしれません。
めぐみ
めぐみは、多恵の前に突然現れた“もう一人の自分”。
最初の登場シーンから、読者の背筋に冷やり…とした感覚を残します。
彼女は圧倒的な行動力でいじめっ子たちに立ち向かいますが、そのやり方は過激で危うさを孕んでいます。
多恵では決してできなかった強硬な態度や、言葉に棘を含ませる場面は、読む者の心をざわつかせるでしょう。
私自身、「味方なのか敵なのか」と何度も心が揺れ動きました。
めぐみは正義と狂気の境界に立つ存在であり、作品の緊張感を最後まで引っ張っていく人物です。
その姿はまるで、仮面をかぶった救世主のようでもあり、破壊者のようでもあります。
そして、読者自身が“もう一人の自分”と向き合うきっかけを与えてくれるでしょう。
もしかすると、めぐみは誰の心にも眠る衝動の化身なのかもしれません。
リリナ
リリナは、物語序盤で多恵をいじめる中心的な加害者です。
彼女の行動は冷酷で、読んでいると胸がざわ…っと騒ぐかもしれません。
しかし物語が進むと、孤立や不安に苛まれる姿も描かれていきます。
強気な態度の裏に隠された脆さを垣間見たとき、単純な悪役ではないと気づくでしょう。
彼女が夜一人で涙を流すシーンを思い出すと、人は誰しも完璧ではなく、弱さを抱えているのだと感じました。
もしあなたが多恵の立場なら、リリナをどう見ますか?
敵として突き放すのか、それとも過去を越えて関わり直すのか。
人間関係の複雑さを映す鏡として、リリナは欠かせない存在です。
彼女の変化は、この物語の核心に迫る鍵を握っているのかもしれません。
杏
杏はリリナや多恵と関わる生徒であり、家庭に問題を抱えています。
父親との関係性や家庭環境が描かれる場面では、読者の心にも重い影を落とすかもしれません。
私はそのシーンを読んだとき、「登場人物一人ひとりに背景がある」という当たり前の事実に気づかされました。
母親不在の寂しさや、父親に対する恐怖がちらりと顔をのぞかせる描写には、言葉を失いました。
杏は作品に深みを加える存在であり、ただの脇役にとどまらない重要な役割を果たしています。
彼女がどう選択し、どのように自分の未来を掴むのか。
その過程は、読者に「自分ならどうするだろう」と問いかけてきます。
彼女の物語を追うことで、読者は自分自身の家庭や人間関係を振り返ることになるでしょう。
そして、彼女の成長が物語全体に新しい色を添えていくのだと感じました。
見どころと印象的なエピソード
物語を語るうえで外せないのが、めぐみが初めてリリナに正面から挑む場面です。
その瞬間、読者は「やっと反撃が始まった」と胸が高鳴るでしょう。
私も読んでいて、ページをめくる手が震えるほどの緊張感を味わいました。
めぐみの視線や言葉の鋭さに、教室全体がピタリと静まり返る描写は鳥肌が立つほどです。
さらに、その後のリリナの動揺した仕草や、机の下でこっそり拳を握りしめるシーンは、これまでの彼女の強気な姿を一変させる瞬間として鮮烈に記憶に残ります。
そして、リリナが予想外の表情を浮かべる場面では、これまでの立場が逆転するような爽快さと戸惑いが交錯します。
その表情の微妙な変化を読み取るたびに、読者は「人はこんなにも脆いのか」と考えさせられるでしょう。
もうひとつ印象的なのは、杏の家庭のシーンです。
母親が部屋を案内しながら話す場面では、笑顔の裏に潜む恐怖がじわ…と伝わってきました。
照明の暗さや家具の配置までが圧迫感を生み出していて、読者の心まで締め付けられる感覚になるのです。
ここで初めて、彼女の心の闇がしっかりと描かれ、単なるサブキャラクターではないことを実感します。
家庭という閉ざされた空間に潜む圧力や孤独が、物語に深い陰影を与えているのです。
そして、このシーンを読むと、現実の家庭のあり方にも思いを馳せずにはいられませんでした。
また、多恵が自分の弱さと向き合いながら成長していく小さな瞬間も見逃せません。
たとえば、彼女が教室の片隅で小さな声を絞り出す場面は、一見些細でも大きな一歩に感じられます。
その声は震えていても、確かに未来への扉を開くきっかけになっているのです。
私はその描写を読んだとき、自分自身の過去の体験を思い出し、胸の奥がじんわり熱くなりました。
一歩を踏み出すことの重さと尊さを、多恵の行動が教えてくれるように感じました。
さらに、作品全体に漂う「もう一人の自分」との対話というテーマは、読者に強い余韻を残します。
夢の中に迷い込んだような不思議な感覚で、登場人物と自分の境界が曖昧になる瞬間もあるでしょう。
あなたもきっと、「もし自分だったら…」と心に問いかけられている感覚になるでしょう。
それは単なる想像を超えて、現実に生きる自分自身を深く見つめ直す時間になるかもしれません。
エピソードひとつひとつが鋭く胸に突き刺さり、読後も長く記憶に残るはずです。
そして、物語の細部に散りばめられた小さな仕掛け――廊下に落ちた一枚の紙切れや、ふとした会話の言葉の端々――が後の展開に繋がっていくことで、読者は驚きと納得を同時に味わいます。
この物語の見どころは単なる逆転劇や刺激的な展開にとどまらず、登場人物の心の襞を細かく描き出している点にあります。
彼らの感情の変化を丁寧に追うことで、まるで自分も物語の一員になったような没入感が生まれるのです。
そして最後には、読む人の未来への考え方までも静かに変えてしまう可能性があるのです。
作品を閉じたあとも、自分の心に問いかける声が残り続けるでしょう。
パラサイト・ドールあらすじと感想レビュー

↑当サイト作成イメージ画像
感想レビューから見る作品評価
「パラサイト・ドール」を読み終えたとき、胸の奥に残るのは単なる爽快感ではなく、不思議な後味でした。
いじめに立ち向かう痛快さと、めぐみの行動が生む不穏さの両方が、心を揺さぶってくるのです。
正義と復讐の境界線が揺らぐたびに、「本当にこれでいいのだろうか…」という疑問が浮かびました。
その感覚は、物語が進むにつれて強くなり、読者自身の価値観を静かに問い直してきます。
私自身、登場人物の葛藤を追ううちに、善悪の単純な二分では語れない人間の奥深さを感じました。
多恵の心の弱さと強さ、リリナの表と裏、そしてめぐみの狂気と正義のはざま。
それぞれの立場に触れるたび、簡単には答えが出せない現実の人間関係が重なって見えてきました。
そして、作品を閉じた後もなお、登場人物たちの表情や言葉が頭から離れませんでした。
特に、教室の中で交わされるさりげない視線や、夜の静けさの中で響くモノローグは、読後も心に残り続けます。
こうした余韻の深さが、長く読者の心に残る理由のひとつなのでしょう。
さらに、作画や演出の巧みさも無視できません。
めぐみが放つ一瞬の微笑みや、リリナの揺れる瞳といった細やかな描写が、読者に強烈な印象を与えています。
私もページをめくるたびに、まるで映像作品を見ているかのような臨場感を覚えました。
背景の描き込みや小物の配置にまで神経が行き届いており、そこにキャラクターの心理が映し出されているように思えます。
また、ストーリーのテンポも独特で、時に静かな間を挟みながら緊張感を高めていく構成には、作り手の計算された巧妙さを感じました。
これらの要素が合わさって、単なる復讐劇では終わらない“人間そのものを描く物語”に昇華しているのかもしれません。
読者の心をざわつかせ、時に優しく包み込み、また突き放す――そのリズムこそが、この作品の魅力だと感じます。
読後には、ただ物語を読んだというよりも、自分の心の奥に隠れた影や光を見せられたような感覚が残りました。
面白くないと言われる理由
一方で、「重苦しい」「読んでいて疲れる」と感じる人もいるかもしれません。
確かに、作品には残酷な描写や心を締め付ける展開が多く、娯楽的な軽さを求める人には厳しく映る可能性があります。
ときに描かれる暴力的なシーンや、心理的に追い詰められる描写は、気持ちを沈ませることもあるでしょう。
めぐみの行動が行き過ぎに見えたり、正義なのか狂気なのか判断に迷う点は、読者にとって不快感になることもあるでしょう。
そのため、「面白くない」と評価されることがあるのも事実です。
さらに、展開が予想外の方向に進みすぎて、読者が混乱することもあります。
物語が意図的に読者の期待を裏切る構造になっているため、テンポの速さや陰惨さに疲労感を覚える人もいるでしょう。
しかしその違和感こそが、この物語の核心にあるのではないでしょうか。
私は「単純に楽しませてくれない物語だからこそ、逆に強烈に記憶に残るのだ」と感じました。
作中で描かれる息苦しさや重苦しさは、読者の心に大きな負荷をかけます。
ですが、その重さを背負ってこそ得られる理解や共感があるのかもしれません。
むしろ、その厳しさを受け止めたときに初めて、自分の人生に重ねて考えられる余地が生まれるのでしょう。
つまり、面白くないと評される部分も、実は作者が仕掛けた大きな狙いなのかもしれません。
私自身、読後に感じた複雑な感情は、むしろ作品の価値を高めているのではないかと考えました。
そうした二面性を受け入れることで、物語の深みをより鮮明に味わえるでしょう。
そして最後には、「自分はどちらの立場に共感するのか」という問いを、読者一人ひとりに残していくのです。
作品を振り返ると、その問いがいつまでも心に響き続けるのではないでしょうか。
作中に登場する名言とその意義
「私が生きるのは、私のため」――この言葉は、物語の中盤で多恵が心の奥から絞り出すように放った一言です。
その瞬間、読者は彼女の成長を実感し、自分自身の人生に重ねて考えるきっかけを与えられるでしょう。
私はこの場面を読んだとき、胸の奥がじんわり熱くなり、過去に自分が言えなかった言葉を代弁してもらったような感覚になりました。
こうした名言は、単なる台詞を超えて、読者の心に響く“指針”のような役割を果たしているのです。
一方で、めぐみの「正しさなんて、誰が決めるの?」という冷たい言葉も忘れられません。
この台詞は、正義と狂気の間で揺れる彼女の存在を象徴しており、読者に深い思索を促してきます。
彼女の冷淡な眼差しとともに放たれたその一言は、物語の空気を一瞬で張りつめさせ、読者自身の価値観を問い詰めるような迫力を持っていました。
さらに、脇役たちの短い言葉にも印象的なものがあります。
杏がつぶやいた「私はただ普通でいたい」という声は、過酷な環境に置かれた人間の切実な願いとして響きました。
その声には弱さと強さが同居していて、読者は「もし自分が同じ立場ならどう答えるだろう」と考えさせられます。
また、教師の何気ない言葉や、登場人物が心情を漏らす瞬間の一言が、後の展開に繋がっていく場面も多くあります。
小さな台詞の積み重ねが物語全体に厚みを与え、印象的な名言をさらに引き立てているのです。
名言が登場するたびに、物語は単なる娯楽から一歩踏み込み、人生を見つめ直す鏡のような役割を果たしているのではないでしょうか。
読者はキャラクターの言葉を通して、自分の過去や未来を考え直すきっかけを与えられるのです。
そして、その言葉の数々は物語を閉じた後も心の中で反響し続け、人生の岐路でふとよみがえるかもしれません。
無料試し読みができるおすすめサイト
電子書籍を楽しむ上で「どのサイトを選ぶか」は非常に重要です。
その中でも特におすすめしたいのが、コミックシーモアの試し読み機能です。
まず、扱っている作品の数が豊富で、漫画はもちろん、ライトノベルや小説まで幅広く揃っています。
そのため、自分の好みにぴったり合う一冊を見つけやすいでしょう。
また、サイトの操作性が非常にシンプルで、初めて利用する人でも迷うことなく読み進められる点が高く評価されています。
通勤中の電車の中や、寝る前のちょっとした時間など、どんな場面でも快適に利用できるのは大きな魅力です。
さらに、試し読みできるページ数が他のサイトより多めに設定されていることもあります。
物語の雰囲気やキャラクターの魅力をじっくり確かめられるので「購入してから思っていたのと違った」という後悔を避けられるでしょう。
そして、コミックシーモアでは定期的にお得なキャンペーンが開催されています。
新規登録時の特典や割引クーポン、さらにはポイントバック企画など、賢く利用すれば出費を抑えて楽しめるのです。
「少しでもお得にたくさんの作品を読みたい」と思っている人にとって、このサービスは大きな味方になるはずです。
また、スマホやタブレット、パソコンといった複数のデバイスに対応している点も便利です。
場所を選ばずに自分のペースで作品を楽しめる自由さは、現代の読書スタイルに合っています。
試し読みを通じて作品の世界観に触れ「続きをすぐに読みたい」と思えたとき、そのままスムーズに購入できる流れも快適です。
結婚や恋愛をテーマにした漫画を探している人には、特におすすめできるサービスだと言えるでしょう。
あなたもまずは気になる一冊を試し読みして、自分の心に響く物語と出会ってみませんか。
なぜ人気? 成功の理由を解説
「パラサイト・ドール」がこれほど支持を集める背景には、複合的な魅力が存在しています。
まず挙げられるのは、スリルと心理描写の両立です。
次の展開を予測できない緊張感が続く一方で、登場人物の心の奥にある葛藤や傷が丁寧に描かれているため、単なる刺激だけで終わらない厚みを持っています。
また、作画の美しさや演出の巧妙さが、作品全体を格上げしている点も見逃せません。
私自身、読んでいてキャラクターの心情が一枚絵の中に凝縮されている瞬間に何度も出会い、強い感情の揺れを体験しました。
一枚のコマに込められた緊張や孤独感、そしてふと見せる柔らかい笑みなど、視覚的な力が物語に深みを与えています。
さらに、いじめや自己肯定感といった普遍的なテーマを扱っていることも、多くの読者に響いている理由だと思います。
誰もが一度は感じた不安や孤独を物語に重ねることで、「これは自分の物語かもしれない」と思わせる力があるのです。
加えて、めぐみと多恵という二重構造のキャラクター設定が、物語に強い吸引力を生んでいます。
二人の視点が重なり合い、時に対立し、時に補い合うことで、読者は常に揺さぶられ続けます。
その関係性の揺らぎが新たな緊張感を生み、物語を読む手を止めさせません。
さらに、単なるキャラクター同士の対立ではなく、「自分の中にある光と闇のせめぎ合い」を描いている点も人気の理由でしょう。
作品を読むことで、誰しもが持つ内なる声に耳を傾けざるを得なくなり、深い没入感が生まれます。
つまり、この作品は単なるエンタメを超え、読者の人生観に影響を与えるほどのメッセージ性を持っているのではないでしょうか。
物語の核心に触れるごとに、読者は自分自身の価値観や生き方を問い直すことになるのです。
そして、そうした問いかけが積み重なることで、読後に強烈な余韻が残り、再読を誘うような中毒性を生んでいるのだと感じました。